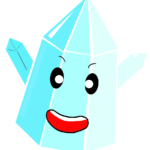967年(昭和42年)、千里ニュータウンはどんな一年だったのでしょうか?
新聞を紐解いてみると、前年に続き、千里ニュータウンの成長とともに行政の不透明な公金使用が露呈。そして、ついに三選を目指していた村田吹田市長が立候補を断念する事態に。
本来なら千里ニュータウンの発展、そして大阪万博という歴史的プロジェクトに関わりたかったはず。しかし、利権まみれの政治に翻弄され、志半ばで去ることになりました。
政治家は市民のことを考えず、親は子供を考えず、地主は小作人を考えない。変な期待はしないほうがいい——そんな戒めのような一年だったようです。
昭和42年1月1日 新年の挨拶

新聞には北千里山駅(現・北千里駅)の完成予想図が掲載され、新年の幕開けを飾りました。
駅前の店舗賃貸募集が始まり、何より話題を呼んだのは 世界初の無人自動改札機 の登場です。
今や世界中で当たり前となった自動改札機ですが、その第一号が 北千里山駅 に設置されたのです。

ちなみに、昭和38年に開業した新千里山駅(現・南千里駅)は、当初バスとの接続が悪く利用者が少なかった(昭和38年の千里ニュータウン参照)。
しかし、北千里山駅は違いました。 「世界初の自動改札を見に行こう!」 という物珍しさもあり、開業直後から利用者が殺到。
その影響でタクシーやバスの利用者が激減し、関係者は渋い顔をしていたとか。
大阪万博まであと3年!期待と不安が交錯

大阪万博まであと3年。
この時点で確約している参加国は 20カ国とも50カ国とも 言われており、過去の万博と比較しても異例のスピードで進行していました。
・ブリュッセル万博(1958年)……43カ国
・モントリオール万博(1967年)……72カ国
目標は モントリオール万博超え 。
当初は「せめてブリュッセル万博以上」としていたものの、すでに上方修正が検討されるほどの勢いでした。

さらに、来場者予測も膨れ上がります。
東京オリンピックの総来場者は200万人、外国人観光客は5万人。
それに対し、大阪万博は 総来場者3,000万人、外国人100万人 を見込んでいました。
「東京オリンピックの10倍どころか20倍になるのでは?」との声も上がるほど。
(実際には、この予想を さらに超える来場者数 となる)

北千里山駅の 自動改札機発表 など、すでに海外から注目される話題が続々と登場。
大阪万博は国内外の関心を一気に集めるプロジェクトへと成長していました。
吹田、幼稚園パンク状態!遊戯室が消える

吹田市の 教育行政のずさんさ が再び批判の的に。
幼稚園は定員オーバーで、 ついに遊戯室が教室に改造される事態 に。
これにより、子どもたちは本来遊ぶべきスペースを失い、親たちの不満が爆発しました。

ある父兄は新聞に 「吹田市の文教行政はあまりに酷すぎる!」 と投稿。
市の教育委員会への批判が一気に高まりました。
村田吹田市長、三選出馬辞退へ

吹田市の行政の機能不全が問題視される中、 「村田吹田市長の三選出馬は絶望的」との見方 が強まりました。
新年の挨拶では「やり残したことを実現する」と意気込んだものの、すでに時遅し。
「村田下ろし」 の動きが加速し、市長選には 6人の候補が出馬予定 。
これまでの悪政を徹底的に糾弾され、ついに正式に 出馬辞退 を表明することになります。
千里ニュータウンの歩車分離、吹田側は後手に

千里ニュータウンの理想の一つ 「歩車分離」 。
ところが、吹田市側の整備は まったく進んでいない 状況でした。
南千里山(現・南千里)、北千里山(現・北千里)ともに、 駅前ロータリーは従来のまま 。
「一体、歩車分離の構想はどこへ行ったのか?」 との声が新聞に掲載されました。
この3年後に完成する 千里中央駅 では、タクシーやバス乗り場を完全に分離し、
東西南北に陸橋を設置することで 「本当の歩車分離」 を実現することになります。
しかし、昭和42年の時点では、まだまだ吹田市側の対応は後手に回っていたようです。
吹田側の最後の住区名が内定するも…?

千里ニュータウンの吹田市域における 最後の住区名 が決定しました。
- E地区 …… 北桃源台
- D地区 …… 南桃源台
しかし、しばらくして 正式名称が変更 されます。

- E地区 …… 竹見台
- D地区 …… 桃山台
ところが、これが 物議を醸す ことに。

竹見台へ転居予定の住民が 田舎の両親に新住所を伝えたところ、「竹藪の中に住むのか!」と怒られた という話が新聞に掲載されました。
「千里ニュータウンのイメージにふさわしくない」との苦情が続出。

それでも、5月・6月には 一気に入居者が押し寄せる だろうと予測されています。
昭和42年の幕開け、すでに混乱の兆し

北千里山駅の開業や大阪万博の期待が高まる一方、
吹田市の行政は 混乱の極み 。
市長の辞退、幼稚園問題、歩車分離の遅れ——
千里ニュータウンが発展するにつれ、行政の対応の遅れが浮き彫り になっていました。
エリート市長に期待!

吹田市の新市長に当選したのは 山本治雄氏 。
・北野高校卒
・東京大学卒
・司法界出身
というまさに エリート街道まっしぐら の人物でした。
彼が掲げた公約は、これまで後回しにされていた 教育・都市計画の改善 。
・「全員幼稚園入園」の実現
・パンク状態の小学校問題の解決
・歩車分離の徹底
・行政の闇の完全撤廃
これまでの ずさんな行政運営にメスを入れる姿勢 を見せ、市民の期待が高まりました。
盆踊り、夜店で真夏の夜を満喫

昭和40年の 異様な熱気 に包まれた盆踊りに比べると、
昭和42年はだいぶ落ち着いた雰囲気になってきたようです。
この年、新聞には 佐竹台の盆踊りの様子 が掲載。
一方で、 一番規模の大きい南センターの盆踊りは記事にもならず 。
「千里ニュータウン最大の夏祭り」という熱狂的な盛り上がりも、
少しずつ落ち着きを見せ始めていたようです。
村田市長は去ったが、「開かずの施設」は残る——責任は誰に?

佐竹台のサブセンター 、つまり ショッピング施設 が 空室のまま放置 されていました。
しかし、建設費用として借り入れた 利子は年間200万円 。
本来なら、ここからの家賃収入で利子を賄うはずが、 空室が続いているため完全に赤字 。
「そもそも、なぜサブセンターを建設したのか?」
昭和37年に千里ニュータウンの入居が始まり、
佐竹台マーケットもオープン。
しかし、すぐに経営難に陥ったはずの佐竹台マーケットに、 さらにサブセンターを追加 。
明らかに 不要な施設を建設 し、結果的に 税金を垂れ流し た形に——。
「千里ニュータウンの失敗は、日本の行政の縮図」
そんな厳しい指摘が新聞に掲載されました。
吹田市の闇が暴かれる!
村田前市長が去った後、次々と行政の問題が明るみに。
① 公文書改ざん & 裏金問題

・土地代金に関する公文書契約で 裏金が発覚
・ 大阪府知事と吹田市長が関与 していた疑惑
② 天下り問題

・ 定年後の大阪府職員が吹田市に大量天下り
・ 「吹田市は大阪府の食い物にされているのでは?」 との指摘
昭和40年の段階では 「政治家なんて市民のことなど考えない」 という言葉が皮肉に聞こえたが、
ここにきてそれが 現実のものとなった 形に。
津雲台・藤白台で「電話教室」開催

ダイヤル式電話が普及し始めたものの、
「正しくかけられない人が多すぎる!」 という問題が発生。
・途中でダイヤルを離してしまう
・十分に回しきれず、交換手につながらない
その 失敗率は約4割 。
つまり、 10回かけて6回しか正しくつながらない という状態だったのです。
「せっかく電話が開通したのに、これでは意味がない!」
ということで、 「電話教室」 を開催。
今でいう 「スマホ教室」 のようなものでしょうか。
ちなみに、 この時代の電話はまだ大阪市内へ直通できない 。
交換手を通す必要があったため、操作ミスが増えてしまったようです。
電話売ります——「転売ヤー」登場

電話の普及とともに 「電話権利の売買」 が急増。
早く電話を手に入れたい人たちのために、 転売ビジネス を始める人々が現れました。
「電話開通が待ちきれないなら、ウチから買いませんか?」
組織的に電話権利を買い取り、売り出す 転売業者の広告 まで登場。
まさに、今の プレイステーションやiPhoneの転売 に通じるものがありますね。
「部屋なき亭主族」に朗報! 2LDK登場

当時は 「戦後、強くなったのは女と靴下」 なんて言われた時代。
ニュータウンの団地に入居したものの、
間取りが2K(2部屋+キッチン) で、 「亭主の居場所がない」 という悩みが続出していました。
そこで登場したのが 「2LDK」 。
・リビング(L)
・ダイニング(D)
・キッチン(K)
という間取りが 初めて導入 され、 「これで亭主の居場所ができる!」 と喜ばれました。
御堂筋線の延伸、前途多難

千里ニュータウンのさらなる発展に向け、
地下鉄御堂筋線を江坂から延伸する計画 が進行中。
しかし、 吹田・春日町付近の「動かしがたい墓地」が問題に 。
用地買収が難航し、地元では 「この墓を動かせば祟りがある」 との声も——。
新聞には 立ち退き予定の墓地の写真 が掲載され、
まさに 「複雑怪奇な地元事情」 が浮かび上がりました。
どうなる輸送問題——万博の一日輸送人数42万人!

1970年の万博開催まで、 あと3年 。
この年、万博の輸送計画が発表された。
その試算によると、「1日の来場者42万人」 。
「この数、さすがに多すぎるのでは?」
そんな不安の声が各所で上がった。
そして 大阪市が早くも撤退を表明 。
「万博が終わった後、地下鉄の赤字が確実だから協力できない」
と、地下鉄延伸計画に対し、完全に消極的な姿勢を見せたのだ。
しかし、地下鉄は 万博成功の重要な鍵 になるはず——。
新聞は 「年内に用地買収を急がなければ間に合わない」 と警鐘を鳴らした。
「冷飯」の新千里西町——設備が追いつかず、住民苦境

新千里西町では 住宅が先行して建設 され、
学校や商店といった 生活に不可欠な施設がないまま入居開始 。
・買い物をするのに半日がかり
・子どもが通う学校が遠すぎる
住民たちからは 「私たちは後回し?」 という声が続出。
「西町は ニュータウンの中で最も冷遇されている地域 ではないか?」
そんな悲痛な叫びが新聞に掲載された。
7月豪雨で各所で山崩れ——吹田側の分譲地開発に欠陥

この年、7月に発生した豪雨により、
千里ニュータウンの各所で 土砂崩れが発生 。
・青山台などの吹田市側の分譲地が 赤土むき出しの状態 だったため、大雨で崩壊
・府の都市計画の 欠陥が指摘される
「土地開発を急ぎすぎた結果では?」
「安全対策を考えずに住宅ばかり建てたのでは?」
都市開発の 「後手後手の対応」 が、またもや浮き彫りになった。
「女性の美しさはまず下着から」——価値観の変化

戦後間もない頃まで、生活は 「生きるため」 のものであった。
しかし、この時代になると、
「人生を楽しむ」
「美しく生きる」
という価値観が浸透し始めた。
その象徴とも言えるのが 「下着広告の増加」 。
少し前までは 「女性が美を追求すること」は贅沢なこと とされていたが、
この年、新聞にも堂々と 下着の広告が掲載 されるようになった。
千里ニュータウン住民、悲願の信号機設置!

「ようやく、信号機がついた!」
これまで交通事故が多発していた千里ニュータウン。
住民の長年の要望により、ついに 信号機が6ヶ所 に設置された。
設置されたのは以下の場所:
・阪急 南千里駅前
・阪急 北千里駅前
・北消防署前
・佐竹台中央線交差点
・古江台中央線交差点
・藤白台中央線交差点
「無免許運転が横行する千里ニュータウンの幹線道路に、
今まで 信号機がなかったことが驚き だ」と新聞は皮肉を交えて報道。
行政の 対応の遅さ を指摘する声が多かった。
高層住宅、大丈夫か?——桃山台・竹見台の不安
千里ニュータウン 初の高層住宅 として建設された 桃山台・竹見台 。
しかし、住民からは 不安の声が続出 した。

- 「もし火事になったら、消防車はどうするの?」
- 「エレベーターが止まったら大変」
- 「耐震性は大丈夫なのか?」
蓋を開けると 人気はイマイチ 。
新聞も 「住民の不安が先行している」 と報道した。
新設の桃山台小学校、生徒わずか1人!?
「桃山台小学校、開校!」

……しかし、なんと 入学した生徒はたった1人 。
校史に残る開校初年度 となり、新聞も皮肉を交えて報道した。
とはいえ、翌年以降は 急激に生徒数が増加 し、
この開校1年目の状況が「幻のような話」になる。
桃山台小学校開校も生徒1人
校史に残るであろうと新聞は皮肉。
桃山台の「ライフストア」開店も閑古鳥

桃山台にオープンした 「ライフストア」 。
「新しいスーパーができる!」と期待されていたが、
初日以降、まったく客足が伸びない状態 に——。
その理由は:
- 値段が強気すぎる
- 店員の態度が悪い
- ちょっと歩けば南センターの「オアシス」がある
結果、「わざわざ行く必要がない」 という声が相次ぎ、
奥様方からも 「このままでは潰れるのでは?」 と冷ややかな目が向けられた。
プール開き!「カッパ」たちが大賑わい

千里ニュータウンのプールが今年もオープン!
新聞には「カッパ連、大賑わい!」との見出しが躍る。
泳ぐ人=カッパ という表現が、いかにも昭和らしい。
まだ海水浴に行くのが一苦労だった時代。
近場で楽しめるプールは ニュータウン住民にとって貴重なレジャー施設 だった。
とはいえ、当時のプールは今のような 塩素消毒が徹底 されておらず、
シーズン終盤になると 水がやや濁ってくる というのも当時のあるあるだった。
「面白いよ!」——麻雀ブーム、主婦にも波及

この頃、ニュータウンの サラリーマンの間で麻雀ブーム が巻き起こる。
「最近、夫の帰りが遅い……」
心配になった主婦が理由を尋ねると、
「麻雀が面白くて、つい遅くなっちゃうんだ」
「そんなに面白いなら、私にも教えて!」
こうして 主婦たちの間でも麻雀が流行 し始めた。
キャラメルを賭けて勝負するなど、微笑ましいエピソードも。
しかし中には 「嫁の帰りのほうが夫より遅くなることもある」 という家庭もあり、
麻雀を教えた夫が 「余計なことをした」と後悔している という笑い話まで出てきた。
日本脳炎、大阪で猛威——発症すれば致死率40%

昭和40年頃から 日本脳炎が全国的に猛威 を振るっていた。
特に 大阪は全国トップクラスの罹患率 で、
一度発症すると 死亡率40% という恐ろしい病気。
当時は ワクチンも普及途上 だったため、
「とにかく 蚊に刺されないことが最善の予防策 」と報じられた。

ニュータウンでは 溜池や水田の多さ から蚊の発生が深刻な問題に。
「夜は 蚊帳(かや) を張る」
「夕方から 長袖・長ズボンを着る 」
といった対策が呼びかけられた。
ついに大阪直通電話が登場!

これまで千里ニュータウンから 大阪市外へ電話をかける場合 、
交換手を通さないといけない という不便な状態だった。
しかし、この年 ついに直通電話が設置!
・各近隣センター
・駅前
・総合病院
など、計 30ヶ所 に公衆電話が設置された。
「これで いちいち交換手を通さず に大阪へ電話できる!」
と、住民たちは大喜び。
今の時代では考えられないが、電話一本が画期的なニュースになる時代 だったのだ。
新千里西町、有力商人募集!——しかし誰も応募せず

ニュータウン各地に 近隣センターのマーケット が作られたが、
どこも 経営が苦戦 している。
そんな中、新千里西町の近隣センターでは 「誰も入店希望者がいない」 という異常事態に。
そのため、企業局が 「有力商人募集」 という気合の入った広告を掲載。
しかしその字体が 「江戸時代の貼り紙のよう」 だと話題に。
商人たちが敬遠する理由は明確だった。
「あと3年もすれば、新千里東町に 大規模なショッピングセンター ができるかもしれない」
そうなると、わざわざ 西町で開業するメリットがない のだ。
行政が 商業施設の誘致に苦戦している 様子が浮き彫りになった。
南センター、3店舗が相次ぎ閉店——商業の厳しさ

ニュータウン開発当初、南センターは 「商業の中心地になる」 と期待されていた。
しかし、現実は甘くなかった。
「限られた住民数の中で 飽きさせずに商売をするのは難しい 」
開業から わずか3年で、3店舗が立て続けに閉店 する事態に。
特に 家賃が高すぎる ことが経営者の負担になっていると指摘され、
「行政は もっと商店の経営を考えて家賃設定をすべき 」
との不満が噴出した。
ニュータウン、教習車両が「我が物顔」で走行——住民の怒り

千里ニュータウンの 片側二車線道路 は、当時としては珍しい 広々とした道路 だった。
そのため、関西各地の教習所が「絶好の練習場所」として目をつけた 。
しかし、これが住民の怒りを買うことに——。
・千里ニュータウンの住民が普通に生活する道を、教習車両が我が物顔で走行
・右折、左折の 極端な低速運転で渋滞 を引き起こす
・「千里ニュータウンは 教習所のコースじゃない! 」と苦情殺到
住民の怒りの声を受け、新聞も 「住民の生活を考えた行政指導を」 と報道。
しかし、この問題は すぐには解決しなかった 。
公園が大人のゴルフ練習場に——子供たちの遊び場が消える

「楽しめる公園づくり」を掲げたニュータウンだが、
いざ整備されると 大人たちが我が物顔でゴルフの練習を始める という事態に。
「気づけば 子供たちは追い出され、遊び場を求めて彷徨う 」
公園の本来の目的が 大人の私的な練習場 にされることに、
住民の間でも賛否が巻き起こった。
「ニュータウンは子供のための街じゃないのか?」
新聞には 子供を守るべき大人が、逆に子供の場所を奪っている との批判的な論調も。
婦女子を守ろう——佐竹台で防犯協会が対策強化

ニュータウンの人口増加に伴い、 婦女子を狙う犯罪が増加 していた。
特に 佐竹台では痴漢被害が多発 し、
防犯協会が 住民向けに注意喚起を開始 。
当時の団地は 見通しが悪い ところも多く、
また 照明設備が不十分 だったため、
「夜道では特に気をつけるように」と呼びかけられた。
これを受け、住民側も 防犯ベルの配布 や 夜間巡回 など、
自主的な対策を検討し始めた。
津雲台小学校、野鳥保護のため巣箱を設置

「めっきり減った野鳥たちを、昔のように戻したい」
そんな願いから 津雲台小学校が巣箱の設置 を開始。
千里ニュータウンは 開発が進むにつれ緑が減り 、
鳥たちの姿も少なくなっていた。
この取り組みには 「千里野鳥を守る会」 も協力し、
住民からも 「自然との共生を大切にしたい」 という声が上がった。
「NHK集金人に注意!」——横柄な態度に住民から苦情

「NHKの集金人が、女性が玄関に出ると態度がでかくなる」
住民からの投書が新聞に掲載された。
・「恫喝まがいの対応をされた」
・「契約を断ると 威圧的な態度 を取られた」
という苦情が相次ぎ、 NHKの集金方法が問題視 された。
これから約50年後、
「NHKをぶっ壊す!」と叫ぶ政党が登場することを考えると、
すでにこの時代から NHKの集金トラブルは問題になっていた ことが分かる。
買い物指南——賢い消費者になれ!

この時代、日本は 高度経済成長の真っ只中 。
しかし、豊かになったとはいえ、
「お金の使い方が上手くないと、結局損をする」という問題があった。
そんな中、新聞では 「賢い買い物の仕方」 を指南。
・「立地の良さやブランドではなく、品質を見極める力を持とう 」
・「広告やセールに惑わされず、本当に必要なものを買う」
・「店を選ぶより、自分の目を養え」
今でいう 「賢い消費者になろう!」 というメッセージ。
この考え方は 現代にも通じるものがある 。

ここまで見て、この記事が昭和42年をシンプルに表しているように思った。
大人は子供を大事にしないし、
ビルオーナーは店子を大事にしない。
政治家は市民を大事にしない。
そう、期待せず自ら利口になるしかないのだ。
今にも、そして未来永劫通じるメッセージのように思える。
春までは選挙、政権交代問題が多かった。
輝かしい昭和37年からの6年間、当時の市長は何をしていたのか?
最後まで、そして辞めてからも無駄な設備の為銀行に利子を払い続けなければならない負の遺産を残した。
今回当選した市長は北野高校→東大卒という点でエリート市長と期待が寄せられている。
まずは慎重に信号機設置などに着手。
今後どうなっていったのか注目したい。
まとめ
昭和42年の千里ニュータウン——理想と現実のはざまで
この年、千里ニュータウンは 開発の拡大とともに矛盾が噴出 した一年だった。
北千里駅の開業とともに 世界初の自動改札機 が導入され、万博へ向けた期待が膨らむ一方で、 信号機の不足、幼稚園の定員オーバー、インフラ整備の遅れ など住民の不満が続出。
4月、新市長に東大卒の 山本治雄氏 が就任。前市長の不透明な行政を批判し、 「全員幼稚園入園」「歩車分離の徹底」 を掲げるが、課題は山積みだった。
また、 ショッピングセンターの閉店、ニュータウン内での教習車両の横行、公園がゴルフ練習場化 するなど、住民の暮らしに影響を与える問題が相次いだ。
万博まであと3年。急ピッチで進む開発の中で、千里ニュータウンは 理想の街から、現実の街へと変化 し始めていた。
次回は昭和43年でお会いしましょう!