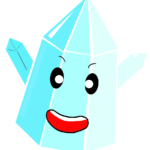エルトンジョン:オールタイムランキング TOP75

35位 ”Sorry Seems to Be the Hardest Word” (‘Blue Moves,’ 1976)
ジョンには悲しい曲がたくさんあるが、
冒頭の “What have I gotta do to make you love me?” という問いかけからして、
この曲は絶望の淵にある。
絶望の淵から語りかける
“Sorry Seems To Be the Hardest Word “というフレーズは
エルトンの哀愁漂うゴージャスなマイナー調のメロディーライン、
悲しげな歌声でさらに悲しく感じられます。
そして続いていく、
バーニーの夢も希望もない絶望的な歌詞。
この曲は聴くのではなく、
エルトンの心の奥底にもぐりこんで、
エルトンの絶望感に夜明けが来るよう、願うだけで良いのです。by – メリンダ・ニューマン
34位 ”My Father’s Gun” (‘Tumbleweed Connection,’ 1970)
ザ・バンドの『ミュージック・フロム・ビッグ・ピンク』(主にカナダのバンドがアメリカーナに挑戦)とは異なり、
本作が収められた『タンブルウィード・コネクション』は、
アメリカ南部の神話に取りつかれた2人のイギリス人の若者(エルトンとバーニー)が描いたアルバムである。
当時、ヒッピー文化が全盛で、
ある種の古き良きアメリカ回帰が流行っていたが、
エルトンとバーニーは一時の流行を追いかけるのではなく、
本気で憧れていたバーニーの世界観に息を吹き込むべく
作曲とボーカルの表現法にこだわった。
南軍の兵士になろうとする若者の視点から歌われたこの曲は、
当然ながら敬遠されるかもしれない。
しかし、「My Father’s Gun」は、
ゆっくりとした展開、ソウルフルなボーカル、軽快なホーンによって、
息子が父親を葬り、自ら死に直面する覚悟をするという痛み、喪失、厳しい決意が
詳細に描かれている出色の作品であることに誰も意を唱えないだろう。by – J.L.
33位 ”Song For Guy” (‘A Single Man,’ 1978)
エルトンの今回の75thカタログの中でも、
本作は特にシングルの中では異例中の異例といえるだろう。
「Song For Guy」は7分間の最後の部分を除いてインストゥルメンタルで、
歌詞は後半の “Life isn’t everything “という一節のみ。
そこに到達するまでは、遊び心がありながらも憂鬱なピアノと不気味なシンセサイザー、
そしてあまり楽しそうでないローランドのボサノバ調の繰り返しで構成されています。
エルトンのロケット・レコードの10代のバイク・メッセンジャーであり
事故死した少年「ガイ」捧げられたというタイトルの謂れを聞けば、
途端に胸に突き刺さる本作品。
アメリカでは評価されずコケた作品。
イギリスでは理解され、彼らしくないトップ5のヒット。
普段のアメリカ高イギリス低のエルトンの評価が
正反対となったことも興味深い、、、 by – A.U.
32位 ”Grey Seal” (‘Goodbye Yellow Brick Road,’ 1973)
1970年にエルトンの自身のアルバム用に録音されていたこの曲。
しかしながら、実際に世に広まるのは1973年の『Goodbye Yellow Brick Road』
世界のエルトンファンは初めての作品と認識している最中、
実は彼の一部のバンドスタッフは、
「Grey Seal」はエルトンの最初期の作品と認識しているという、
ズレを生じてさせている作品なのだ。
結果的にそれはいい判断だった。
73年版の『Goodbye Yellow Brick Road』に収録するという壮大なアレンジは、
この曲を楽しい軽薄なものから、
99%のライブパフォーマーにとってセットリスト必須となる曲へと昇華させた。
歌詞の意味合いははまだ少し不可解だが
(流星がなぜできるのか習ったことはない。
私はただ、擦り切れて破れた学校で農作業をしていただけだ)という歌詞の本意について。
「教えてアザラシ!」と正気に戻るころには拳を突き上げることだろう。by – A.U.
31位 ”Crocodile Rock” (‘Don’t Shoot Me I’m Only the Piano Player,’ 1973)
エルトンにとって、
初の全米No.1ヒットとなった「クロコダイル・ロック」は、
彼のディスコグラフィーの中で常に特別な位置を占めている。
この曲では、ファルフィサ・オルガンがユーモラスに歌い上げ、
子供の頃のエルトンにインスピレーションを与えた
ロックミュージックへのノスタルジックなオード(頌歌)となっている。
(それがエルヴィス)
「クロコダイル・ロック」は実際、
ジョンの最も遊び心にあふれた曲で、
コーラス後のフィーリング・グッドヴァイヴスの波に乗って、
今やクラシックとなったメロディーライン。
ライブでは常に観客が合唱する作品となっている。by – S.D.
30位 ”Burn Down the Mission” (‘Tumbleweed Connection,’ 1970)
エルトンの3枚目のアルバム「Tumbleweed Connection」の最後を飾るこの曲は、
音楽的に最も複雑な曲のひとつで、
6分の間にテンポやキーを変えながら演奏される。
2分を過ぎたあたりから、
ジョンは激しいピアノを弾き始め、
ジューク・ジョイントから飛び出してきたような、
バレルハウス風の騒々しい間奏を披露する。
ポップス、ジャズ、カントリーの要素を取り入れたメロディーは、
ジョンの多彩な才能を表している。by – M.N.
29位 ”Curtains” (‘Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy,’ 1975)
「We are fall in love sometimes」は、
長年の作詞家バーニー・トーピンへの優しいオマージュですが、
“Curtains “はもっと不可解な曲です。
二人が最初に書いた「Scarecrow」を含む初期の作品への言及が内容に含まれているが、
タイトル「Curtains」は何かの終わりを示唆している。
エルトンとバーニーは、「自分たちが20世紀の名声の絶頂期にいる」こと、
あるいは、彼らのコラボレーションが
(一時的に)終わりを告げようとしていることを把握していたのかもしれない、、、
それは1977年に起こったことである。
ジョンはかつてこの曲を「たわごと」と断じたが、
宗教的な体験に近いものがある。
「轟音ドラム、ベース、ギター、スリリングなハーモニー、
そしてレイ・クーパーのチューブラー・ベル・フィルが
曲の最後を華麗に飾っているのだ。by – フランク・デジアコモ
28位 ”Empty Garden (Hey Hey Johnny)” (‘Jump Up!,’ 1982)
エルトンが
“The kick inside is in the line that finally gets to you
And it feels so good to hurt so bad. “(限界を超える苦しみは最後に君に与えてくれる。それは痛みから得ること)と
「Sad Songs (Say So Much)」で歌っているように、
親友ジョン・レノンを追悼するこの曲は、
ビートルズ亡き後1年半を経て発表されたにもかかわらず、
強烈な喪失感を放っている。
この曲の力強さは、
エルトンの軽快な演奏と、
歌詞にある不毛なニューヨークの庭の描写(これは、1974年にエルトンがマディソン・スクエア・ガーデンで行ったレノンの最後のライブを指していると解釈する人もいる)から生まれている。
しかし、カタルシス(心洗われる感情)を与えてくれるのは、全開のコーラスだ。
“ノックしても、誰も出てこない…ああ、ずっと君を呼んでいるのに
ねぇねぇ、ジョニー、もう、遊びに来てくれないのかい?”と。
もう、来ない事がわかっているからこそ、より一層、胸が締め付けられる。by – F.D.
27位 ”Honky Cat” (‘Honky Chateau,’ 1972)
「Honky Cat」はエルトン初期の陰鬱で繊細なピアノマンというイメージが一変し、
明るく光を放った瞬間である。
カーニバルのようなホーンとエレクトリック・ピアノに支えられ、
ファンクやグラマラスな雰囲気が漂い、
“Your Song” や “Tiny Dancer” のような意図的に地味な初期のヒット曲とは
一線を画す明るく軽快なサウンドを作り出している。
この曲でジョンはユーモア、フラッシュ、キャンプを得意とすることを明らかにし、
エルトンのポップ・インペリアル期における
出発地点(グラウンド・ゼロ)となったのである。by – S.T.E.
26位 ”I Guess That’s Why They Call It the Blues” (‘Too Low For Zero,’ 1983)
I Guess That’s Why They Call It the Blues」は、
ブルースナンバーではないのにも関わらず、
エルトンがニューオリンズ直系のイージーローリングなピアノフィルを散りばめているのがミソだ。
スティーヴィー・ワンダーも同様で、
モータウンで過ごした10代の頃を思い起こさせるようなハーモニカのソロを聴かせるなど、通常のブルースとは一線を画すサウンドを聴かせてくれる。
ジョンの揺れ動くメロディーのおかげで、
「I Guess That’s Why They Call It the Blues」はブルースのように聴こえる。
後悔に満ちた嘆きのフレーズが、
重苦しいものではなく、むしろ心地よく感じられる。by – S.T.E.